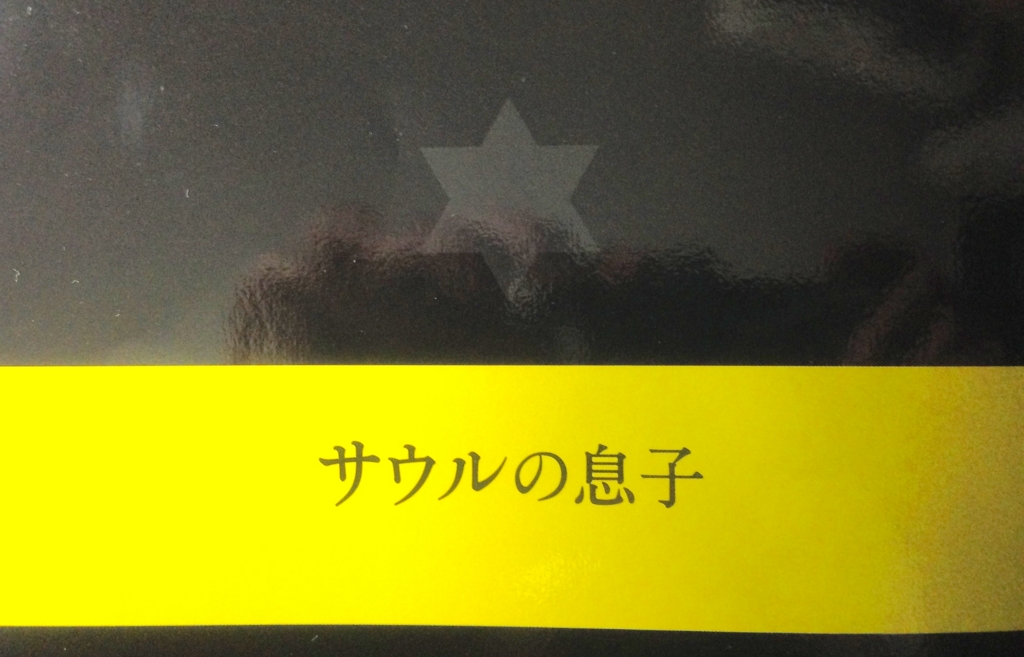
衝撃的な映画でした。こういう映像体験は初めてかもしれません。
(以下、ネタバレあります。)
カンヌでグランプリをとった作品です。ホロコーストが題材。アウシュビッツでユダヤ人をガス室に送りこみ、後始末をする実作業は、同じユダヤ人たちがしていました。彼らはゾンダーコマンドと呼ばれていたそうですが、彼らもまた数ヶ月後には殺される運命にありました。主人公のサウルはそのゾンダーコマンドの一人。サウルは、ガス室で生き延びるも、その後殺されてしまう少年が自分の息子と知り(ほんとうに息子なのだろうか?)、その息子をユダヤ教の戒律に従って土葬してラビに祈りを捧げてもらおうとします。しかし、強制収容所の中でそんなことができるはずもなく、というか、そんなことをすこしでも考えること自体がおかしいくらいの状況なのに、サウルはこだわり、少年の遺体を布に包んで自分の寝床に運び、ラビを探し、折から起こったゾンダーコマンドたちの暴動の最中に土に埋めようとし、かなわないと見ると、遺体を肩にかついで森に逃げ……。
そういう映画です。
「カメラワークのこと」
映画手法的になにがすごいかといえば、サウルの視点での、あるいは、サウルの顔を大きく入れた、手持ちカメラによる映像でほぼ全編を構成していること。

(『サウルの息子』劇場用パンフレットより、撮影風景。)
画面の半分以上を占めるサウルの顔や背中の周囲に、ピントの合わない周辺の光景が映るのですが、ピントが合っていなくても、それが衣服を脱がされた男女子供のユダヤ人たちであることはわかり、あるいは、すでに殺された屍体であることはわかるのです。白々とした屍体の形に陰部が黒く浮かび、さりげないカットの隅に女性屍体の乳房が見えたりします。サウルたちの仕事は、その屍体を片付け、汚れたガス室の床を掃除することなのです。観客であるわれわれは、サウルとともにアウシュビッツの中にいて、彼のすでに感覚が麻痺したような無表情を見せられながら、山のような屍体の処理をしているような気になってきます。焦点の浅いカメラは、ぼんやりとその屍体を写すのですが、そのピンボケは、サウル自身の見たくないものへの意識の表われなのかもしれません。
とにかく、この映像体験がすごい。息もつかせぬストーリーや爆破シーンの連続などで、ぐったり疲れる映画もありますが、ああいう疲れとはまた少しちがって、常にじわじわと見たくないものが目の前にある恐怖に慣れていく恐怖といえばいいのでしょうか。
「息子を葬る」
この撮り方は、小説でいえば、三人称主人公視点なのだと最初は思いました。サウルの表情はほとんど常にスクリーンにあるので、サウルの視点とは言い切れないのですが、しかしサウルのいる周囲しか描けない描き方なのです。しかし、結局、サウルの心の中はよくわからないのですから、主人公視点ではあるのですが、それはカメラの目であるというだけで、主人公に共感していくような描き方ではないのです。そもそも、サウルがなぜこんな奇妙な行動をとったのかは、いまひとつ理解できません。屍体を焼却されることはユダヤ教の戒律に反しているそうなので、ユダヤ人抹殺への抵抗の象徴なのでしょうか。サウルというのは、調べてみると旧約聖書に出てくるユダヤの王様の名ですが、息子たちとの関係で、なにか象徴的なものがあるのかといえば、そうでもなさそうです。詳しい方がいれば教えてください。
ラスト近くで、森に逃げこんだゾンダーコマンドの男たちが廃屋に隠れているところを、近所の男の子がのぞき、その子とサウルの目が合います。サウルは、かすかに微笑むのですが、この微笑みの意味はなにか? 殺された自分の息子と重ね合わせて、努力は無駄ではなかった、こうして会えたじゃないか、という微笑みなのか? それとも、宗教的・民族的な縛りを超えた、なにか人間として、少年の生きる輝きのようなものに対しての達観した微笑みなのか?
「多言語映画」
この映画は、ハンガリー人のネメシュ・ラースローが監督し、ハンガリー人のルーリク・ゲーザという俳優・詩人・神学教師がサウルを演じています。ゾンダーコマンドたちは、周辺の国々から集められたユダヤ人の中で健康で屈強な男たちが選ばれるので、さまざまな国籍の人たちがいて、それぞれの国籍ごとに班を作って作業しています。サウルがハンガリー人なので、ハンガリー語が主となっているようですが、よくわかりません。東欧ユダヤ人のあいだで使われるイディッシュも混じっていそうです。ロシア語は多少聞きとれました。ポーランド語も出ているようです。ドイツ軍将校たちはドイツ語です。字幕はどうなっているかというと、サウルの周辺のハンガリー語、将校たちのドイツ語にはほとんどついているようです。ロシア語は( )付きでした。
この映画は音の処理にも凝っていて、周囲の男たちの話し声やユダヤ人の悲鳴やガス室の中で扉を叩く音や、それが消えていく静寂や、銃声や、土にショベルを突き立てる音や、もろもろの音がステレオで左右から聞こえてきます。当然、人の声は、上にあげたような言語のどれかなのでしょうが、日本人であるわれわれにはほとんど内容がわかりません。ですが、この映画をドイツ人が観たら、あるいは、ロシア人が、ハンガリー人が観たら、それぞれがわかる声を拾っていくはずです。各国での上映では、どの言葉に字幕をつけるかという判断もむずかしいでしょう。複数の言語を解する観客はより深く映画を理解するかもしれません。そもそも、カンヌで上映した時はどうしたんでしょうか? 英語の字幕を部分的につけたのでしょうか? それともフランス語?
「ホロコーストを描くということ」
わたしの訳した児童書の中にも、いくつかホロコーストに関連するものがあるわけですが、戦後70年ですから、そろそろ実際に体験した世代がいなくなってしまうので、もう、関連する作品が出ても今がピークではないか、と、十年くらい前から思っているのですが、こうしてまた新しい描き方をした作品が発表されます。監督のネメシュ・ラースローは1977年生まれですから、まだ39歳。でも、親戚がホロコーストで亡くなっているという血の問題はあります。拙訳『フェリックスとゼルダ』の作者モーリス・グライツマンも同じで、祖父が第二次大戦中に迫害を経験しています。
それはわかるのですが、70年をすぎた今、当時の出来事を今を生きている世代と関連づけて描くのではなく、この映画は、むしろ、今までのホロコースト映画よりも格段に現場に接近、というか、没入する描き方をとっているところに監督の強い意志を感じます。風化していく記憶にまっこうから抗って、観客にアウシュビッツを体験させようとする映画を作ったところに、この映画の大きな価値があります。
目をそむける、というのが人間の本性だと思います。忘れたい、というのが人情です。しかし、欧米の知識人の中には、ホロコーストだけでなく、奴隷問題や東西冷戦やベトナム戦争や、すでに教科書の中にしかないように思える題材を掘り起こし、新しい手法で切り取る人たちが次々に出てくるのがすばらしい。「知識人」という言葉は陳腐ですが、知性というもののあり方を感じるところです。
翻って、日本では、ということになりますが、頑張っている人はいると思うし、応援したい。また、こうした視点の作品を翻訳していきたいものです。戦争や差別に関する作品は、つい、「ああ、またか」と思ってしまいがちですが、必ずしもそうではないことが、この映画を見るとわかります。まだまだ、いろんな切り口があるのだと。
そして、日曜の朝10時の有楽町ヒューマントラストシネマは、ほぼ満席。12時、2時の回の予約状況も残席わずかの印が……。小さめの映画館とはいえ、この映画を見に来る人がこんなにいるというだけで、捨てたもんじゃない、とも思いました。
(M.H.)